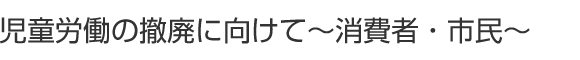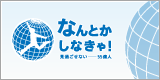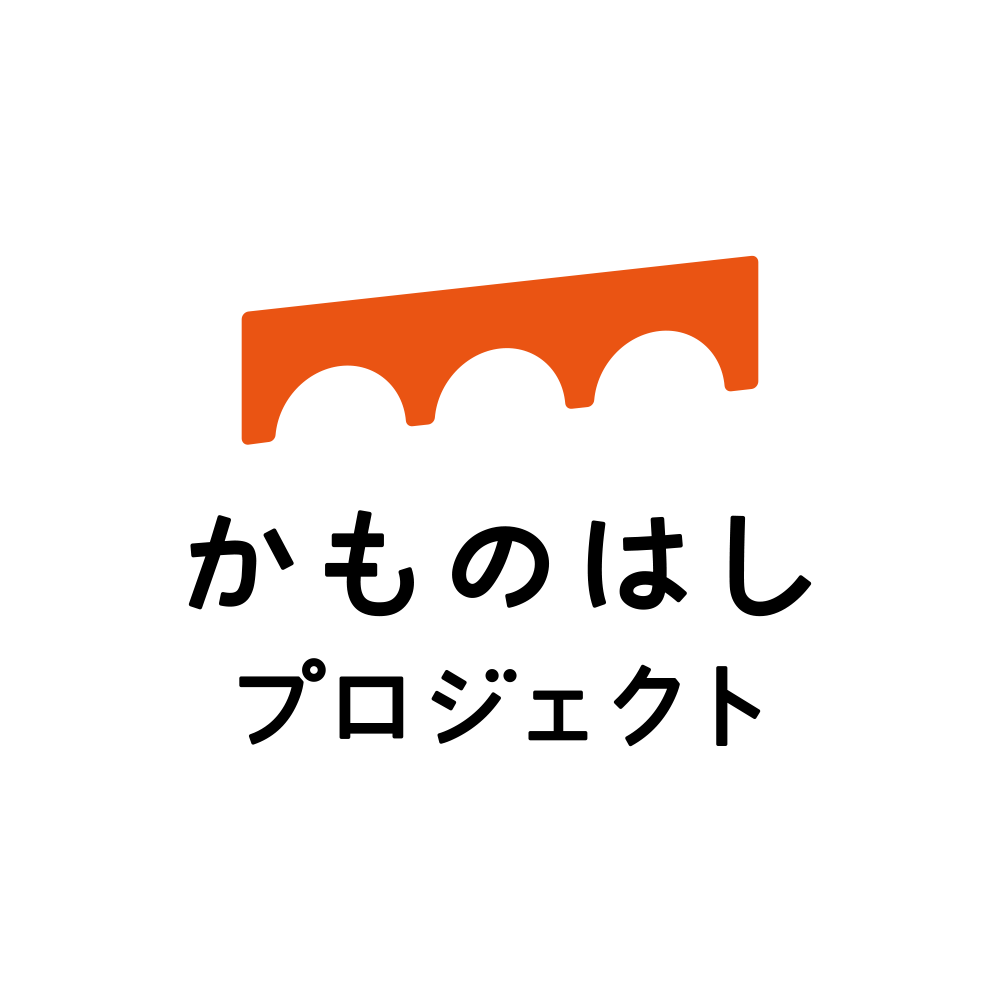児童労働は、子どもたちの権利を侵害し、健やかな成長と未来を奪う深刻な問題です。私たち消費者や市民一人ひとりがこの問題に関心を持ち、責任ある行動をとることが、児童労働のない社会の実現に向けた大きな力となります。
1. 消費者・市民の責任と役割
私たちの消費行動は、遠く離れた国の子どもたちの生活と深く結びついています。児童労働が生み出される背景には、依然として貧困や、安価な製品を求める市場の圧力があります。
- 貧困と児童労働の連鎖: 大人に十分な収入と安定した仕事がないために、子どもが家計を支えるために働かざるを得ない状況があります。
- コスト削減と安価な労働力: 農業や製造業の現場では、生産コストを抑えるために、大人よりも賃金の安い子どもが労働力として求められることがあります。
消費者が価格の安さだけを追求し、製品がどのような環境で作られているかに関心を持たなければ、結果としてサプライチェーンの末端で子どもたちが不当な労働を強いられることになりかねません。
私たち消費者は、購入する商品やサービスが、児童労働を含む人権侵害や搾取によって生み出されたものでないか、その背景に関心を持つことが重要です。企業に対して、透明性の高い情報開示と、児童労働をはじめとする人権侵害のないサプライチェーンの構築を求めることで、児童労働の撤廃に大きく貢献することができます。これは、持続可能な開発目標(SDGs)の目標8「働きがいも経済成長も」、特にターゲット8.7「2025年までの児童労働の撤廃」の達成にもつながる行動です。
2.世界と日本の動向と市民の活動
1990年代に大手企業の下請け工場での児童労働が明るみに出て以降、欧米を中心に消費者のボイコット運動が活発化しました。これを契機に、企業の社会的責任(CSR)や人権尊重への意識が高まり、様々な取り組みが進められてきました。
- 企業の行動規範・労働基準の策定と遵守:
- 1990年代後半から、「SA8000」(Social Accountability 8000)や英国の「Ethical Trading Initiative(ETI:倫理的貿易イニシアチブ)」など、児童労働の禁止を盛り込んだ国際的な労働基準や企業の行動規範が策定されました。これらの基準を遵守し、サプライチェーン全体での人権尊重に取り組む企業は増加傾向にあります。
- 近年では、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、企業が自社の事業活動やサプライチェーンにおける人権への負の影響を特定し、防止・軽減する「人権デューデリジェンス」の法制化が欧州を中心に進んでおり、日本企業にも対応が求められています。
- フェアトレードの広がり:
- 開発途上国の生産者に対してより公正な価格を保証し、持続可能な生産と生活を支援する「フェアトレード」の認知と市場は世界的に拡大しています。フェアトレード認証製品を選ぶ消費者の増加は、児童労働や劣悪な労働条件の改善に貢献します。
- 市民や自治体が主体となってフェアトレードを推進する「フェアトレードタウン」運動も、世界中で広がりを見せており、地域ぐるみでの意識向上と行動を促進しています。日本でも2011年に熊本市が日本およびアジアで初のフェアトレードタウンに認定されました。2025年には、鎌倉市が新たに認定され、日本国内で7件目となりました。これらの自治体では、行政、企業、市民団体などが連携し、地域全体でフェアトレード産品の普及や啓発活動に積極的に取り組んでいます。また、これらの認定都市以外にも、フェアトレードタウンを目指す動きが日本各地で広がっています。
- エシカル消費の浸透:
- 人や社会、環境に配慮した消費行動である「エシカル消費」という考え方が、日本でも徐々に広がりを見せています。消費者庁も普及啓発に取り組んでおり、フェアトレード商品だけでなく、オーガニック製品、リサイクル製品、地域社会に貢献する商品など、より広い視点での選択が推奨されています。
3. 消費者・市民の力、課題、多様なセクターとの連携
私たち一人ひとりの消費行動は、企業の方針に影響を与える大きな力を持っています。
- 企業への働きかけ:
- 製品やサービスの生産背景や、企業が児童労働防止のためにどのような方針や行動規範を定めているかについて問い合わせ、意見を伝えることは、企業に児童労働のないクリーンな調達を促す上で非常に有効です。
- ソーシャルメディア(SNS)などを活用して、児童労働問題に関する情報を発信したり、企業の取り組みを評価・共有することも、社会全体の意識を高める上で重要です。
- 課題:
- 製品のサプライチェーンは複雑化しており、消費者が個々の製品の生産背景を完全に把握することは依然として困難です。企業による情報開示のさらなる透明化が求められます。
- 安価な製品を求める市場の圧力は根強く、倫理的な配慮が価格に反映された製品が、必ずしも全ての消費者に受け入れられるわけではないという課題もあります。
- 多様なセクターとの連携の重要性:
- NGO/NPOとの連携: 児童労働問題に関する調査、啓発活動、現地での支援プロジェクトを行うNGO/NPOの活動を支援することは、問題解決に向けた直接的・間接的な貢献となります。
- 行政との連携: 欧州連合(EU)がフェアトレードを政策として支援したり、各国政府が企業のデューデリジェンスを法制化するなど、行政の役割は非常に大きいです。日本においても、政府や自治体がエシカル消費を推進し、企業の人権尊重の取り組みを後押しするような政策を強化することが期待されます。
- 企業との連携: 企業が積極的に児童労働撤廃に取り組み、その情報を消費者に分かりやすく開示することで、消費者はより責任ある選択をしやすくなります。NGOや消費者団体と企業が対話し、協力して問題解決にあたることも重要です。
4. 日本の消費者・市民にできること
日本に住む私たちにも、児童労働の撤廃に向けてできることはたくさんあります。
- 関心を持ち、学ぶ: まずは児童労働の問題について知り、関心を持つことが第一歩です。報道やNGO/NPOの情報、関連書籍などを通じて理解を深めましょう。
- NGO/NPOを支援する: 児童労働ネットワーク(CL-Net)のような専門機関や、児童労働問題に取り組むNGO/NPOの活動を寄付やボランティアで支援することは、現地の状況改善や啓発活動の推進につながります。
- フェアトレード商品・エシカルな商品を選ぶ:
- コーヒー、紅茶、チョコレート、コットン製品など、フェアトレード認証ラベルが付いた商品を選ぶことは、生産者の持続可能な生活を支え、児童労働の予防に貢献します。
- フェアトレードの認知度は、2008年のチョコレボ実行委員会の調査では17.6%でしたが、近年の各種調査では上昇傾向にあり、特に若い世代を中心に高まっています。しかし、欧米しょこくではフェアトレード認知度が80〜90%と非常に高い水準にあるにもかかわらず、日本では、30%〜50%程度で推移している言われており、さらなる普及が望まれます。
- フェアトレードの考え方を家族や友人に伝え、広めていくことも大切です。日常の買い物で生産背景を意識するきっかけになります。
- 企業に声を届ける:
- 自分がよく利用する企業に対し、製品の原材料調達方針や児童労働防止策について問い合わせてみましょう。消費者の声は企業を動かす力になります。
- 企業のウェブサイトやCSR報告書などで、サプライチェーンにおける人権への取り組みを確認し、積極的に情報を開示している企業や、具体的な対策を講じている企業を応援しましょう。
- 行政に働きかける:
- お住まいの自治体に対して、フェアトレードタウン認定を目指すよう働きかけたり、公共調達において倫理的な配慮を求める意見を届けることも有効です。
- 国に対して、企業の人権デューデリジェンスの法制化や、児童労働撤廃に向けた国際協力の強化を求める声を上げることも重要です。
- フェアトレードタウン運動に参加・推進する:
- 日本でも、フェアトレードタウンの数は着実に増えています。お近くのフェアトレードタウンの活動に参加したり、まだ認定されていない地域では、認定に向けた運動を仲間と始めることもできます。