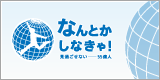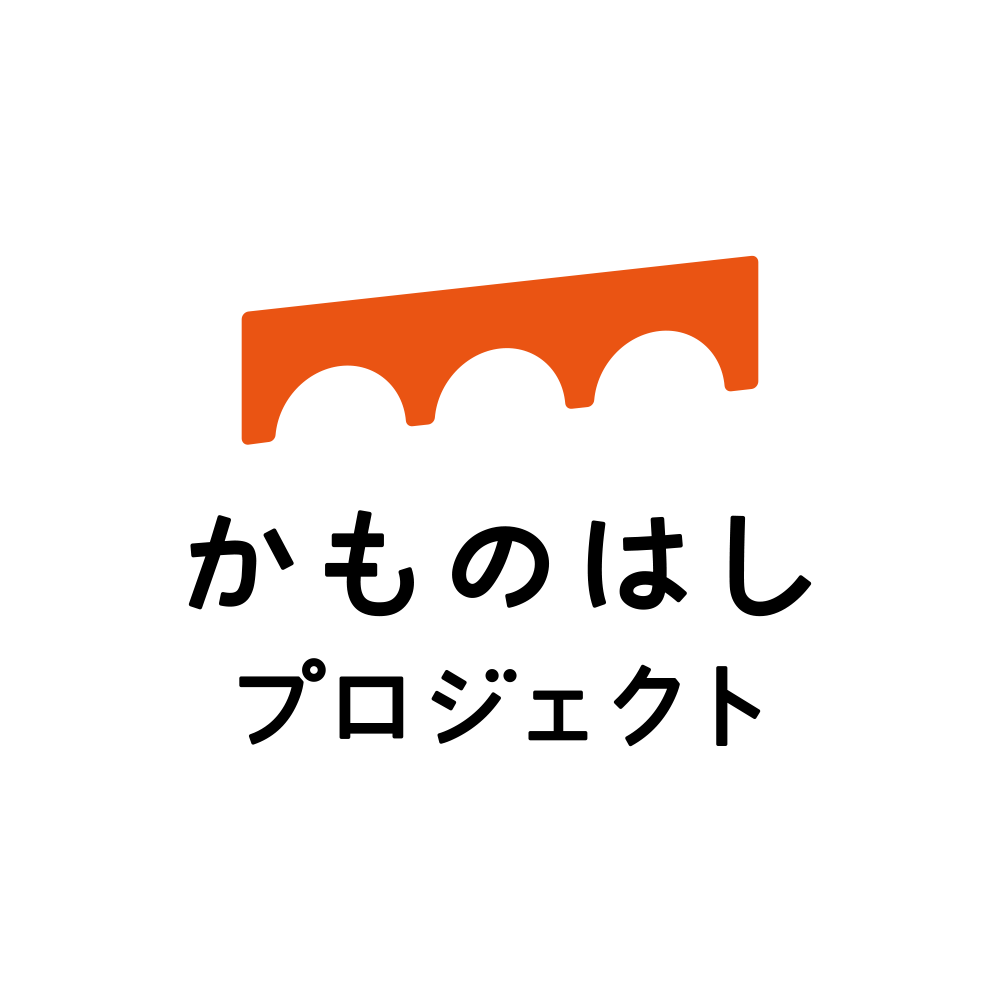1.責任・役割
国際機関は、基本的人権の尊重・推進をその任務の主なものとして掲げています。児童労働に深く関わる国際機関としては、国際労働機関(ILO)は国際的労働基準の策定・各国の条約遵守の取り組み促進の一環として児童労働に関する国際的な取り組み推進を行っていますし、国際児童基金(UNICEF)は子どもの権利保障の一環として児童労働問題に取り組んでいます。児童労働は、子どもの権利条約にある子どもが経済的搾取や危険な労働から守られる権利、教育を受け権利などへの権利侵害だからです。
2015年に合意された「持続可能な開発目標」の目標8ターゲット7には「8.7 強制労働の廃絶、現代の奴隷制および人身取引の廃止、子ども兵士の募集と使用を含む最悪な形態の児童労働を禁止及び撤廃するために、緊急かつ効果的な措置を実施する。そして、2025年までにあらゆる形態の児童労働を終わらせる。(ACE訳)」とあり、上記2つに限らず国際社会として児童労働の撤廃に対する責任を担っています。1999年企業の社会的責任の国際基準として策定された「国連グローバル・コンパクト」にも「児童労働の実効的な廃止」が掲げられており、国際社会へ撤廃を働きかける役割も担っています。
2.2. 活動(現状)
国際機関は主に 1.児童労働についての調査研究、2.国際基準・ガイドラインの策定・推進、3.国際的なアドボカシー・キャンペーン、4.現地での児童労働撤廃のための取り組み、を行っています。
1については4年に一度、ILOがUNICEFなどと協働して児童労働の世界推計を含め、児童労働に関する現状・進展、政策・取り組み、今後の展望などの世界的俯瞰を提供する「グローバル・レポート」を発表しています。他、各国際機関がそれぞれの専門分野に関連する報告書を出しています。ILOは基本的に4年に一度開催される児童労働世界会議の準備、運営にも深く関わっています。
2.については、ILOが第138号条約(就業の最低年齢)及び第182号条約(最悪の形態の児童労働)、国連子どもの権利委員会が「子どもの権利条約」の批准奨励・効果的な実施や監視をしています。98年にはILOで「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」が採択され、児童労働の撤廃は仕事に関わる基本的人権と再確認され、各国はたとえ条約を批准していなくてもこれら原則を遵守する義務があります。また182号条約は2020年ILO史上はじめての全加盟国批准を達成しています。
3.については、ILOは毎年6月12日を児童労働反対世界デーと定めており、世界中で集中的な広報・啓発活動が行われています。日本では、児童労働ネットワークが毎年児童労働に関するキャンペーンをこの日前後に行っています。
また、SDG8.7を推進するためにできたグローバル枠組みが Alliance8.7(アライアンスハッテンナナ)です。
異なるステークホルダーの調整と協力を促し8.7の達成に導くことを目的に、2016年9月に発足し、現在カ国がパスファインダー国として加盟、420のパートナー組織(政府機関、労働組合、NGOなど)が登録しています。またアクショングループを関係国際機関が担っており、サプライチェーン(ILO)、移住(IOM,UNICEF)、法の支配とガバナンス(OHCHR)、 紛争と人道支援(UNICEF)があります。
また4年に一度行われる国際会議では宣言文が採択されそれが世界的な指針となっています。2022年に南アフリカで開催された第5回児童労働撤廃世界会議では、Durban Call to Action(ダーバン行動要請)が採択されました。
4.については、ILOの技術協力プログラム「国際児童労働撤廃計画」(IPEC)が1990年代に創設されて以降、ILOが多くの現地プロジェクトを担っているほか、UNICEFも各国で取り組みを進めています。ILOはこうした国際協力のプロジェクトの多くは各国政府からの支援で成り立っており、国際的な資金減少は大きな課題となっています。
代表的なものとしては、アフリカの児童労働の増加を背景にオランダ政府が資金提供しアフリカ複数国で実施されているILOのACCEL AFRICAなどがあります。ILOは2023年-2025年の活動枠組みも示しています。
3.特徴及びタセクターとの連携
国際機関の特徴は、世界全体の基準やガイドラインを策定し、推進するという世界的・普遍的な枠組みを作成することです。世界各国は、そうした基準・ガイドラインを遵守することを求められていますが、世界全体を一律の方法によって実施するのではなく、それぞれの状況に対応した実施が効果的と理解されています。世界全体を観察・監視する位置にいる国際機関は、世界での「好事例」を提示し、各国にその模倣をうながすことができますので、目標に向けての大きな推進力となっています。 国際機関のプロジェクトの多くは現地のNGOをプロジェクト実施団体としており、NGOとのパートナーシップにより実現しています。またILOは児童労働プラットフォームを運営しており、企業のサプライチェーンにおける児童労働撤廃に向けた協働をしています。
4.日本の取り組み
日本は、上記2に述べたILO2条約、国連条約を批准しています。従って、条約を実施する法的義務がありますが、児童労働の国内法での定義づけ、また児童労働数のデータなどが未整備であり、国内行動計画も策定していません。法令遵守を実質担保する主要国内法としては労働基準法(特に年少者の部分)、児童買春・ポルノ禁止法などがあり、18歳未満が特殊詐欺に使われることなど含め日本国内でも児童労働が存在しますが、認識が低いのが課題といえます。
ILO駐日事務所は荻野目洋子さんをアンバサダーに任命し児童労働に関する啓発活動に力を入れています。ILO活動推進議員連盟、ユニセフ議員連盟なども存在し、児童労働や子どもの権利に関する国内の世論喚起や政府への働きかけなども行っています。
日本政府はUNICEF、ILOにも拠出をしており、児童労働に関するプロジェクトをILOを通じて支援しています。