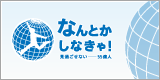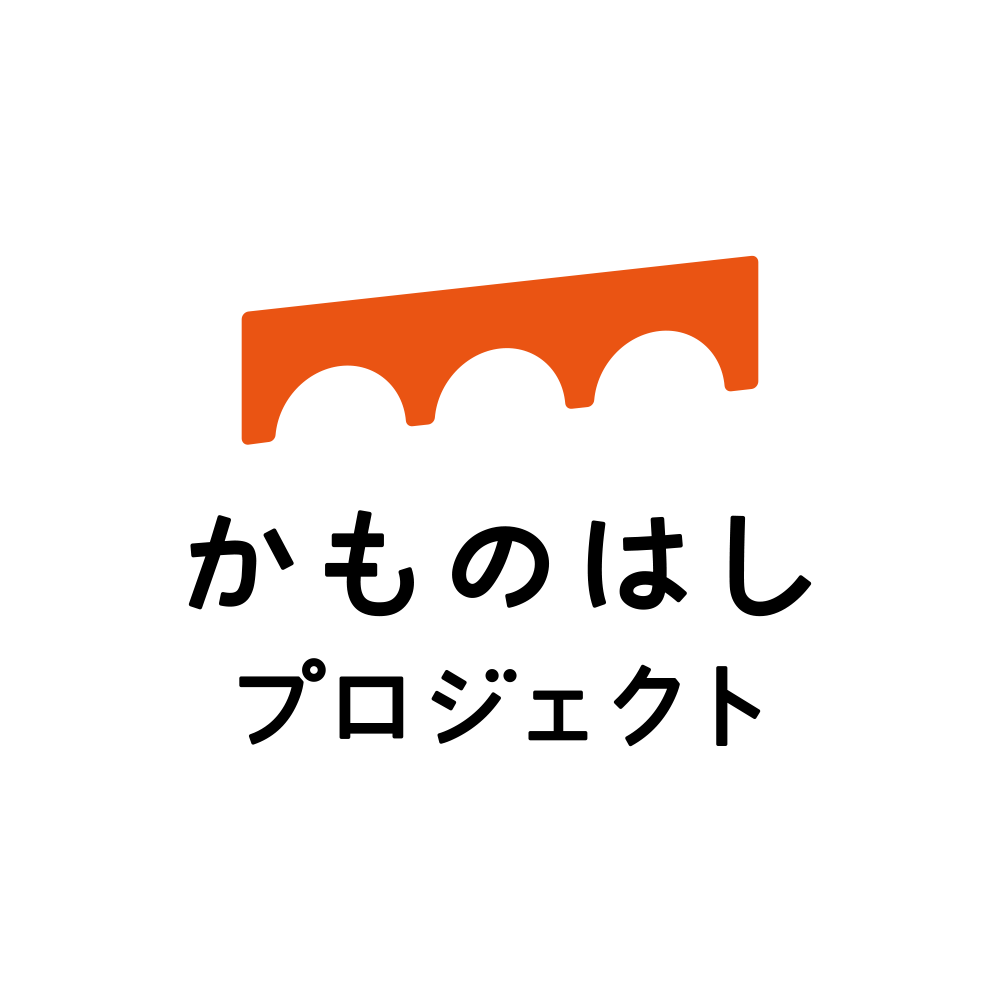1. 責任・役割
労働組合は労働者を代表する組織であり、民主的な職場と全ての労働者にとってのディーセントワークを実現することを目標として、日々活動しています。
児童労働は、大人に代わる安価な労働力として搾取を目的に導入されますが、こうした賃金のダンピングと大人の失業が貧困の度合を深め、更なる児童労働を引き起こす元凶となります。こうした負のサイクルを断ち切るために、国際労働機関(ILO)をはじめとしたグローバルレベルのみならず、国や地域レベルでも、政労使による児童労働撤廃に向けて取り組んでいます。また、先進国においては、労使協議・交渉を通じて、児童労働が使用されていない原材料・製品の調達を確立することで、企業の社会的責任(CSR)を推進する責務を負います。
2. 活動(現状)
政策策定においては、ILOの場に政労使の一当事者として、各国のナショナルセンター(日本では連合)や、国際労働組合総連合(ITUC)、国際産別組織(GUFs)が参加しています。児童労働撤廃のための重要な国際条約であるILO第138号条約(最低就労年齢)や第182号条約(最悪の携帯の児童労働)は、こうした政労使の三者構成機関で採択されたものです。
CSR推進にむけた労使協議・交渉は、ナショナルセンターと使用者団体、産業別組合組織と業界団体、企業別労働組合とその企業との間で行われており、一方で地域コミュニティーを対象とした現地プロジェクトは、その地域の組合のイニシアティブで行われているものもあります。
3. 特徴、課題、他のセクターとの連携
労働組合は上述の通り、労働者を代表する組織であるため、労働組合がある職場においてその強みを発揮する反面、児童労働が蔓延している労働組合がない職場では、充分な力を発揮するのは困難です。このため、この分野で強みを持ったNGOや地域コミュニティーとの連携が必要となります。
NGOと労働組合の連携による国際協力活動は多岐にわたり、物品を通じての協力から海外での共同事業運営まで、様々な場面で協力・連携しています。
| 1. 物品を通じての協力 | NGOで販売しているフェアトレード製品やカレンダーを購入したり、NGOに物品の寄付を行う方法があります。組合でNGOの物品を購入したり寄付を取りまとめたり、組合員へのチラシ配布等の広報協力を行うことで、NGOの活動や現地の人たちの生活を支援できます。 |
|---|---|
| 2. 資金協力 | NGOが支援地で実施している開発プロジェクト(教育、保健衛生、植林、村づくりなど)や緊急救援に資金協力をすることは、貧しい人たちの生活向上や、権利を奪われた人たちの人権擁護につながります。 |
| 3. スタディツアーを通じての協力 | 数多くのNGOが、海外の支援地や様々なNGOの活動現場を見て回るツアーなどを行っています。 |
| 4. 海外での共同事業運営 | 国際協力活動に熱心な労働組合では、NGOとの共同事業を海外で運営している事例もあります。 |
| 5. 意識啓発・キャンペーン | NGOは、児童労働や教育、保健衛生、HIV/エイズ、政府開発援助(ODA)、人権と平和などの国際的な問題について、様々なキャンペーン活動を実施しています。また学習会を開催し、途上国の現場の状況と支援活動について一般市民の方に伝えています。労働組合として、NGOのキャンペーン活動に賛同し、講演会やイベントの講師にNGO関係者を招いて国際協力問題について学ぶことは、組合員一人ひとりの意識変革につながります。 |
一方で、労働者は消費者であるとともに一般の市民でもあることから、意識啓発を行う場合や、署名活動のような動員を必要とする場合には、そのメンバーシップを有効に活用し得る強みを持っています。
4. 日本での取り組み
日本国内では主にアドボカシー活動と啓発活動を中心に行っています。CL-Netに参画しているNGOとも連携しながら、G7サミットやG7雇用労働大臣会合などの機会をとらえ、児童労働撲滅に向けたアドボカシー活動を行い、啓発活動においては、CL-Netが行っているレッドカードアクションに毎年連合としても協力しており、連合に加盟している企業別労働組合、産業別組織、地方連合会がそれぞれレッドカードを掲げアクションに参加しています。また、CL-Netが開催しているシンポジウムにも積極的に参加しており、児童労働撲滅に向けた連合、および連合が1989年に設立した公益財団法人 国際労働財団(JILAF)の取り組み(主に草の根支援事業)などについて共有しています。